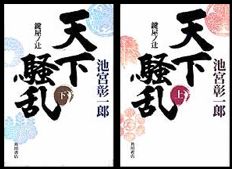|
|
|
|
當山開基 鳥取池田藩城代家老 倉吉荒尾家霊廟 |
|
|
本堂右室中に御奉安の倉吉荒尾公の坐像と位牌13基です。 満正寺は、元禄十二年(1699)夏、『満正院殿別峯恕心居士(まんしょういんでんべつぽうじょしんこじ)』【倉吉荒尾二代宣就(のぶなり)公】の十七回忌の時に、三代秀就(ひでなり)公が現在の地に開山創建されました。 荒尾氏は、本姓を在原氏といい、尾張国知多郡荒尾谷より興るといわれ、戦国時代終り頃、成房(ナリフサ)公と隆重(タカシゲ)公の兄弟が池田氏に仕え、外戚として重く用いられます。 寛永九年(1632)池田光仲(ミツナカ)〈当時は幼少であった〉が岡山藩から鳥取藩にお国替えとなり幕府との交渉を成房の息子、嵩就(タカナリ)公【後に、隆重の養子・倉吉荒尾初代】が勤め、三十二万石として減禄を免れた功績は池田藩にとって多大なものとなりました。 |
|
|
くらよしじんやえず 倉吉陣屋絵図 |
|
|
鳥取入藩後は、嵩就公は、初代倉吉荒尾となる、自分手政治として倉吉陣屋を政庁にし、鳥取藩の組士四十人余と自分の家臣を常住させ倉吉町を支配しました。寛永十七年(1640)に元服していた光仲を初めて国表に迎えるため、江戸藩邸に向い翌年共に帰国する。慶安元年(1648)光仲十九歳、正式にお国入りし、藩主権力確立するために、親裁を開始するが、老臣荒尾成利(米子荒尾)と摩擦対立の間に入り周旋に勤めた。晩年に、光仲は功を賞し、隠居料千五百石と合力米五百俵を与えられる。戒名を『透関院殿練翁祐心居士(とうかんいんでんれんおうゆうしんこじ)』、透関は満正寺の山号「透関山」となっています。 二代宣就公は、寛文七年(1667)の幕命による江戸杉金堀普請の難工事を他十人の者と監督に当たり功に証せられ、また質素の風は武具から生活具に至るまで一貫しており、家中に倹約の風儀を奨励することになり、志摩守であったことから、「恕心志摩(じょしんしま)」の名を高められ、民衆からは、「しまさん」と慕われ晩年には、知行石一万石を領した方です。戒名を『満正院殿別峯恕心居士』、満正は寺号「満正寺」となっています。 三代秀就公は二代宣就公の弟で満正寺開基、元禄から享保にかけて発生した災害と進行しつつあった財政難の解決に向け多大な政治力を発揮し知行石一万一千石を領した方です。戒名は『瑞松院殿功山大心居士(ずいしょういんでんこうざんだいしんこじ)』です。 倉吉は荒尾家が領するようになり、初めて倉吉の近世史が始まり、倉吉の地理的設計・町統制を定め、それが今日に至るまで受け継がれています。 荒尾家には、初代・二代によって書かれた三十年間の日記「倉吉万日記」なるものがあります。 今回ご紹介の他にもたくさんの逸話があります。 1699年創建から幕末まで、歴代の倉吉荒尾公の菩提寺として今に伝える位牌です。なお墓所は、満正寺を離れた仲ノ町長谷寺の山腹に歴代頭首の倉吉荒尾家墓所がございますす。 その後、明治の廃藩置県により、荒尾家は男爵となり、東京へ転居され、菩提寺への庇護は、なくなりましたが、現在の境内地は荒尾家の寄進によるものと伝えられております。 |
|